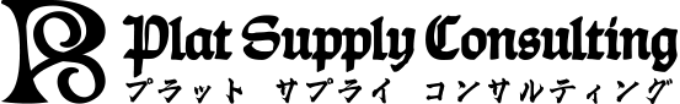Wi-Fi7の実力は
クライアント・サーバ間のネットワーク帯域幅測定ツール『iPerf3』を用いたテスト計測では平均5Gbpsをマーク、「6・6E」を圧倒するハイパフォーマンスぶりを発揮しています。
320MHz(16ch分)広帯域通信が可能に
6GHz帯において『7』では320MHz(16ch分)を実現、従来の160MHz(8ch分)の倍の帯域を利用できます。帯域幅が広くなれば、それだけ多くのデータを送れるようになり速度向上が容易と言われる由縁です。ただし、日本では6GHz帯で利用できる周波数が5925~6425MHzまでの500MHz分にとどまります。
4096QAM(4K-QAM)方式の採用
伝送データの変調方式として新たに4096QAMを採用、従来1シンボルあたり10bitのデータしか送れなかった1024QAMと比較して1シンボルあたり1.2倍の12bitのデータを送れるため速度が向上しています。
MLO(マルチリンクオペレーション)
従来は個別に利用していた2.4GHz、5GHz、6GHzの帯域のリンクをまとめて利用することによりリンクの数だけ速度が上がっています。
実測値の比較
計測では「7」対応のスマートフォンやPCなどのデバイスは現在存在していないため、既存のWi-Fi7対応ルーター2台をそれぞれ接続して速度を計測。10Gbpsの「有線」でPCと接続してルーター間の無線性能をiPerf3にてベンチマークテストしております。
| 一階 | 三階 | |
|---|---|---|
| アップロード(上り) | 1630Mbps | 4580Mbps |
| ダウンロード(下り) | 1460Mbps | 4850Mbps |
近距離(約3mほど)の場合の速度は平均で下りが4.8Gbps前後、瞬間的には5.69Gbpsを達成、長距離(1階と3階)でも下り1.46Gbpsと1Gbpsオーバーを実現できており、距離が離れてもかなり速いのが特長です。
経過秒数ごとの速度変化
計測開始から2秒ほどは3Gbps前後でデータをやり取り、4~5秒前後から徐々に上昇、6秒あたりから計測値がばらつくものの、8秒以降から5.5Gbps前後で安定して稼働している模様が確認できます。
| 経過した秒数 | 下り速度 |
|---|---|
| 1秒 | 3120Mbps |
| 2秒 | 3030Mbps |
| 3秒 | 3050Mbps |
| 4秒 | 4220Mbps |
| 5秒 | 5080Mbps |
| 6秒 | 5160Mbps |
| 7秒 | 4620Mbps |
| 8秒 | 4600Mbps |
| 9秒 | 5400Mbps |
| 10秒 | 5380Mbps |
| 11秒 | 5420Mbps |
| 12秒 | 5430Mbps |
| 13秒 | 5360Mbps |
| 14秒 | 5240Mbps |
| 15秒 | 5260Mbps |
| 16秒 | 5340Mbp |
| 17秒 | 5420Mbps |
| 18秒 | 5370Mbps |
| 19秒 | 5150Mbps |
| 20秒 | 5340Mbps |
導入に向けた課題
まずは製品価格が挙げられます、一般消費者向けであっても一台あたり7~10万円前後はするためハードルが高いのは事実です。ただし対応チップのコスト、10Gbps×2、SFP+、2.5Gbps×2などの有線構成に関するコストや処理を行う高性能なCPU、発生する熱対策、安定した通信のためのアンテナを含めたハードウェアにかかるコストを勘案すれば製品としてにわかに高いとは言い難いものがあります。
導入ポイントとしては、マルチリンクオペレーション(MLO)を用いた超高速な接続に価値を見出せるかどうか?
速度や安定性の向上など投資に対するリターンは確実にあるとは言え安定的運用の実現にはまだまだ時間がかかる見通しです。しかし業務デジタル化やAI時代を迎えつつある経済社会では、情報伝達手段としてのネットワークインフラ整備の重要性はますます高まっており、いつかは対応せざるを得ません。経営者の業務インフラ整備への取り組みへの判断が問われているのです。