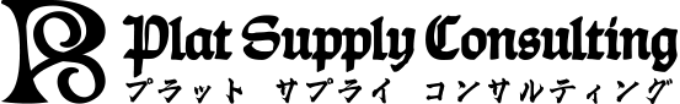次世代ストレージ開発の行方
高速かつ大容量で高品質なディスクとして脚光を浴びてきた「Blu-ray Disk」を大きく上回る記録密度とデータアクセス速度を持つ『HDS(ホログラフィックデータストレージ)」と呼ばれる技術。Microsoft社の研究プロジェクト「Project HSD: Holographic Storage Device for the Cloud」として実用化を目指す動きが活発化しています。今回はこの話題を解説します。
きっかけ
そもそも1960年代初頭に「HDS」技術を提案したのが、インスタントカメラの製造メーカーだった米Polaroid(ポラロイド)社の研究陣。今世紀初頭から研究チームがHDS技術の研究を続け市場投入を目指していました。しかし結果的に商業的成功につながりませんでした。
その後もHDSへの取り組みは続きましたが、大きな変革を起こすことは出来ていませんでした。
開発に際してもCD・DVD状の円盤記録媒体を用いたWORM(Write Once Read Many:書き込み1 回、読み込み複数回)と他の光学メディア製品とあまり変わりばえがせず、競争力を欠くと認識されていたのです。
そんななかHDS実用化に向け、研究プロジェクト「Project HSD: Holographic Storage Device for the Cloud(Project HSD)」をたちあげたのがMicrosoft。
この研究プロジェクトは英国ケンブリッジに所在するMicrosoft Research研究所のラボにて始まり、同研究所では石英などのガラス板へのデータ記録を試みる「Project Silica」も同時に進められています。
異なる指向性
たとえばSilicaでは、WORM(Write Once Read Many:書き込み1 回、読み込み複数回)仕様に基づいた利用が想定されていますが、HSDはデータ消去と再書き込みにも対応、データ読み取り書き込みの速度向上に重点を置いた開発が進んでいます。
いわばパフォーマンスとコスト効率の両方の相乗効果をもたらしつつ機械動作に依存しない耐久性の高いクラウドストレージなどに最適な製品を目指しているのです。またデータ書き換えができなかった以前のHDS製品とは異なり、Project HSDでは記憶媒体に紫外線照射してデータ消去を可能にする技術を採用、その利便性を高めています。
仕組み
従来とほぼ変わらないのは、データ読み取り書き込みプロセスです。
しかし、記録プロセスに関してはレーザー光を二つの信号に分割、「信号光」と呼ばれる一つ目の光信号データを記憶媒体へ運び、運ばれた光線は光情報を処理する空間光変調器デバイスを通過、変調された光線が記憶媒体に照射されます。
「参照光」と呼ばれる二つ目の光信号は空間光変調器を通過せず、鏡に反射、方向転換して記憶媒体に照射されます。その際「参照・信号」光を交差させ記憶媒体に3Dの干渉じまを作り出すのですが、この干渉じまを記録したものを「ホログラム」と呼びます。
一つのホログラムに媒体内の一つの記録領域が割り当てられる仕組みです。
データ読み取り時には、記憶媒体のホログラムに参照光を照射して回折(光線が障害物の裏側に回り込み届く)させ、回折像でデータを再現する手法が取られています。
特長は
記録媒体に立体的にデータを記録できますが、媒体に電気光学結晶を用いた書き込み・読み取りの並列実行でき、これにより読み書き時間は大幅に短縮され、使用部品はHDDより少なく、記録時にも媒体表面だけではなく体積全体を使用できるため記録密度を大幅に高められることが判明しています。
また利用頻度の高いWORM「データ」の読み取り書き込みへのメリットが生まれます。こうしたデータはビジネスアプリで頻繁に利用する「ホットデータ」に比べ利用頻度は高くありませんでしたが、読み書き速度やデータ転送速度などパフォーマンスを上げるには最適と言えるのです。
次世代SSDの鍵となる「PLC」(ペンタレベルセル)化
次に容量増加とコスト削減が進んでいるSSDですが、今や開発に向け取り組みが活発化しているのが「PLC」(ペンタレベルセル)の記録方式。1つのメモリセル当たり5bitのデータを記録できるこの方式では大容量かつ1GB当たりの単価を大幅に下げることができるため、各ベンダは商品化にむけ意欲的です。
さるメーカーの最高技術責任者(CTO)は、『300TB』を超える容量を持つSSDの数年先の登場を既に示唆しています。将来の記憶技術として8bit/セル(OLC:Octa-level Cell)方式まで言及されていますが、現時点で室温状態での6bit/セルの実用化は難しいことが分かっています。商業的に成功するにはまだまだ数々の紆余曲折がある模様です。