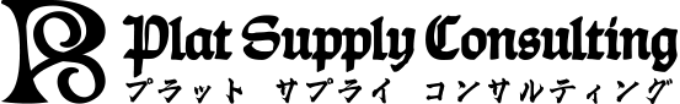「HDD」故障やトラブル対策には
さまざまな用途に活用が進む「HDD」。壊れにくく耐久性が高いとの甘い幻想をいただきがちですが、誤った使い方ややってはいけない利用方法では突然故障するリスクが高い繊細なストレージ。
保管する機密データ等がいきなり消失したら取り返しがつきません。
故障や障害発生につながりやすい原因を事前に把握・確認しておき、万が一に備えた適切な運用体制やリカバリー手順を整備しておくことが必要です。注意しなければならないのはHDDは簡単には壊れないとの思い込みや先入観なのです。
よくある故障は
高温多湿や埃による静電気の発生により損傷を受けやすいのが「プリント基板(PCB)」と呼ばれる電子回路を形成して部品を接続するための基板。
また落下や転倒による強い衝撃や激しい振動などの負荷が加われば磁気ヘッド(データ読み書きを担う部品)がプラッタ(円盤状の記録媒体)に接触する「ヘッドクラッシュ」が発生、プラッタ表面が損傷してデータ損失リスクが生じやすいのです。
また長期間に渡って未使用になれば「スティクション」と呼ばれる磁気ヘッドがプラッタの表面に張り付いてしまう損傷を招きやすく、注意を払う必要があります。長期に渡り使い続けたことによる「摩耗やモーター不良」もよくある故障例。
壊れる前兆傾向
本体内部で故障の原因が生じていた場合、データが消えたり、ファイルが壊れたりと言った予兆が現れ始め、次第にブートエラー(起動時にOSが正常に読み込まれないエラー)が発生するパターンが多いと言えます。ランサムウェア・マルウェアへの感染や不良セクタの増加も同時に疑われる緊急事態です。
予期せぬ異音や異臭・煙、カーソル点滅なども故障やトラブルの予兆が疑われる事態であり、注意深く観察するべきでしょう。
原因
必ずしもハードウェアとは限らず、ソフトウェアを含めた両面からの原因が考えられ、大きくカテゴリーごとに分類できます。
・温度の急激な変動や物理的振動、落雷などの電気ショックよる故障
・内部の機械的故障や搭載部品の不具合
・ソフトウェアやデータに起因する論理的問題
・管理用ファームウェアの不具合や異常
HDDは従来、金属ケースに収められ、一見頑丈そうに思われます。
しかし、環境変動に影響されやすく、高温動作時などは壊れるリスクが高まります。これは冷却用ファン故障や換気不足で引き起こされることが多く、長期間にわたり高温状態が続けば、回路が劣化して素材部品に大きなダメージを与えます。
また自然災害等によりコンポーネントが損傷すれば、使いものにはなりません。
本体が高熱を発してカチカチという音がする場合はオーバーヒートになっている可能性が高いのです。
他にもBIOS画面からHDDを検出できない、もしくはドライブが起動しない際には、通常電圧よりも高い電力が一瞬に電気回路を流れる電力サージが発生している可能性も考えられます。
対策は
まずは室温計などを備え適切な温度や湿度を維持・管理体制を敷いているか?
冬場に発生する静電気等を回避するための除去シートなどを備えているか?
ドライブを安全に保管しているか?
基本的には設置場所を清潔にさせ埃の発生を防ぎ、適切な換気や定期清掃などの管理を行うこと。
電源ケーブルなどを含む配線をわかりやすく、無停電電源装置(UPS)の動作に支障がないよう整理整頓してきちんと整備しておくことが求められます。
次に故障に備えて物理的な異常を見つけたら、状況を注意深く観察すべきです。
たとえばHDDに備わる自己診断機能「S.M.A.R.T.」( Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)を活用した定期・定点観測を行えば、壊れる前に交換すべきタイミングを慎重に見極めることが出来るとともに故障が近いことを事前に察知して交換時期の把握が可能になるのです。