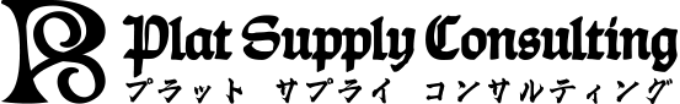「SSD」と「HDD」の優劣比較
磁気ディスクへデータを書き込む「HDD」媒体ですが、近年、容量24TBと28TBのHDD製品が登場、従来型磁気記録(CMR)方式を採用した24TBのものとシングル磁気記録(SMR)方式を採用した28TB。「HDD」大容量化は徐々に進んでいます。
「HDD」の問題点
新たなHDDは、「FC-MAMR」(Flux Control-Microwave Assisted Magnetic Recording:磁束制御型マイクロ波アシスト磁気記録方式)という技術を採用。これはマイクロ波を用いてプラッタの磁性を変化させ、高い密度でデータを記録できることが判明しています。
これまで1つのデータごとに占める領域が大きくなれば、トラック(プラッタを同心円状に区切った記録領域)に保存できるデータ量は小さくなり、HDD1台あたりの保存容量はなかなか大きくならないことが問題となってきました。
また記録領域が微細になるほど磁気ヘッド(データ読み書き用の部品)が精緻にデータを記録することは難しくなることが知られており、プラッタにおける磁性の変化をサポートする「FC-MAMR」技術が必要とされるようになったのです。
「HDD」のメリット・デメリット
SMR方式では、隣接トラック同士の一部を屋根瓦のように重ねて配置、データの記録密度を高め、容量増加に効果的です。一方デメリットとして、対象データの変更時に周囲のトラック書き換えも必要となり、データ書き込み速度低下につながる恐れが高く、バックアップやアーカイブ、読み取り専用と言った一度書き込むだけの用途に向いています。
またインタフェースも「SATA」(Serial ATA)や「SAS」(Serial Attached SCSI)を採用している製品が多く、「SSD」よりもコストが総じて安く、使い勝手がよいメリットがあります。頻繁に利用しないデータを扱う場合、容量単価が高額なSSDのようなストレージでは割に合わないと考えるのは当然のことです。
信頼性が高いのは
1GB当たりの価格は、ストレージ製品のライフサイクル全体にわたる総所有コスト(Total Cost of Ownership;TCO)にも関わります。TCOには主に製品ごとの購入費用、消費電力、メンテナンス費用が大きく影響するからです。
SSDはHDDより1台当たりの価格が高額にはなりますが、メンテナンスコストは低い傾向にあります。
あるストレージベンダーが発表したHDD及びSSDに関する信頼性(システムが提供できるサービスの継続性)データでは、同社の保有する「SSD」の23年第2四半期における年間故障率(AFR)は約1.06%。HDDでは24年第2四半期のAFRは約1.7%との結果が出ているのです。
将来像は
AWSやMicrosoft、Google、Meta等の「ハイパースケーラー」向けに採用が進みつつあると言われているのがフラッシュストレージモジュール「Direct Flash Module(DFM)」製品。ある大手ストレージベンダーはQLC(クアッドレベルセル)方式のNAND型フラッシュメモリ第9世代「Micron G9 QLC NAND」をDFMに大量搭載する計画を発表しており、SSDの容量増大は既に実現が近いのです。
こうしたオールフラッシュストレージベンダーの攻勢が続けば、HDD製品自体の売上や出荷も大きく落ち込む事態も予想され、製品開発も徐々に縮小、HDD製品がなくなる将来もありえます。
これまで大規模データセンター等では、ストレージに価格帯が安いHDDを好んで採用してきました。しかしHDDにはデータ読み書きの速度がSSDよりも遅いデメリットがあります。AI(人工知能)技術の台頭により、使用頻度の低いデータであっても高速にアクセスする必要性が生じハイパースケーラーはSSD活用にかじを切ったと言われています。
従来のSSD容量では、ハイパースケーラーの容量要件を満たすことが出来ませんでしたが、最新世代のQLCフラッシュメモリを採用した容量150TBのフラッシュストレージモジュール「Direct Flash Module」(DFM)が実現、将来的には300TBに達する見込みなのです。
まとめ
TCOの観点から見てデータ・ストレージ管理には、ITインフラ調達、導入、運用管理、保守などのコストが含まれ、ハードおよびソフト、労務管理、ストレージ容量とコンピューティング・リソース、ダウンタイムのコストについても十分な考慮が必要です。
自社に最適なストレージを活用するには、対象IT資産のライフサイクルを通じてかかると見込まれる費用を検討・分析したうえでシステム全体を把握・運用できるだけの知識や能力もまた求められるのです。