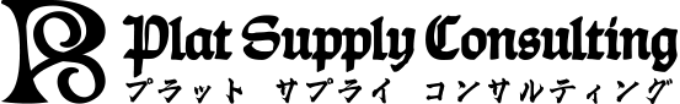高速汎用データ伝送技術「Thunderbolt」の解説
これは外付けドライブやディスプレイとの接続に用いられるデータ伝送規格のこと。もとはLightPeak(ライトピーク)と呼ばれる光インターコネクト技術をベースにインテル社とApple社が共同開発したテクノロジーです。開発を主導したインテルは、2011年LightPeak対応モジュールを商品化させPCおよび周辺機器にも組み込むことを想定していました。
規格の由来
日本語にすると「雷や落雷」を意味するこのワード。実はLightPeakの「光」を用いたI/Oインタフェース規格を『銅線』でも使えるようにしたものです。2011年早春のMacBookPro発表に伴い、この規格が登場しました。要は「光」規格が『LightPeak』、「光と銅線』の新規格が『Thunderbolt』とネーミングされたのです。
『Light Peak』の発表当初は、インテルが『光』への移行を目指していると大きく注目され、特に光通信部品の関連企業では光伝送の時代の幕開けとして『LightPeak』技術への期待が盛り上がりを見せていました。ところがフタを開けてみるとApple製品における『Thunderbolt』は『銅線』が主、『光』は付随的な位置付け。
結果的には光の『LightPeak』に銅線の規格を追加したのが『Thunderbolt』なのです。
背景
インターネットの普及によりネットワークにおける基幹ケーブルは電話網を用いた銅線からネット専用の光ケーブル化への急速な移行がおきましたが、基板や電子機器等には光ケーブル利用はなかなか進まず、現在に至っています。
LightPeakによる10Gbps程度の高速伝送技術実現に『光ケーブル』採用を目指していたインテルですが、『銅』と『光』を併用するThunderbolt規格を受け入れざる得ませんでした。この要因と言われているのが、『光』のコストパフォーマンスの悪さと言われています。10Gbps(5GHz)以下の信号速度においては『銅』にコストパフォーマンスでは軍配が上がってしまうのです。
進化の系譜
| 伝送プロトコル | 最大転送速度 | 最大給電能力 | コネクタタイプ | |
| Thunderbolt | PCI Express 2.0 DisplayPort 1.1a | 10Gbps | 10W | MiniDisplayPort |
| Thunderbolt2 | PCI Express 2.0 DisplayPort 1.2 | 20Gbps | 10W | MiniDisplayPort |
| Thunderbolt3 | PCI Express 3.0 DisplayPort 1.2/1.4 | 40Gbps | 100W | USB Type-C |
| Thunderbolt4 | PCI Express 4.0 DisplayPort 2.1 | 40Gbps | 240W | USB Type-C |
| Thunderbolt5 | PCI Express 4.0 DisplayPort 2.1 | 120Gbps | 240W | USB Type-C |
活用シーン
たとえば活用ケースではThunderboltを用いれば一本で給電から映像出力、データ転送までこなせ、複数のケーブルが必要なくなり、これまでより少ない配線での業務が可能となり、スペースの整理や混雑した状況からよりシンプルかつコンパクトにまとまった環境に改善させることができるのです。
ここまでメリットを記載してきましたが、デメリットとしてあげられるのが「コストの高さ」。Thunderboltポートを搭載するマザーボードを要するPCはそのほとんどが高価、デスクトップ・ノート型モデルを問わずその傾向が見られます。またThunderbolt4のケーブル本体も安いもので4千円前後、ロングタイプは1万円以上もするのです。