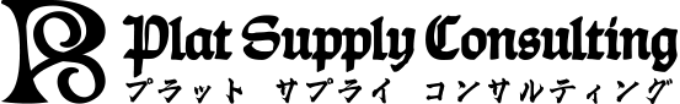システム障害発生への備え
先日も発生した高速道路の「ETC」障害など、影響が広範に及ぶシステム障害は今や珍しいことではなくなりました。
こうしたシステム障害はIT化の進んだ現代社会では実は起こりやすく、被害は広範囲に及びやすいものです。
悪影響を最小限に抑えるには何をどうすればよいのでしょうか?
押さえておくべきシステム障害の要因分析とより効果的な対策を解説します。
障害の要因
一番に考えられるのがハードやソフトウェアの故障や不具合、内在するバグや部品劣化によるものです。落雷からの停電や地震・風水害などの自然災害によるハード・ソフトウェア損傷は重大な悪影響を引き起こす要因となりえます。
次に多いのがケアレスミスなど作業時の見落とし、ネットワークやサーバ等のハード・ソフトウェア設定ミスや設置場所等の運用への考慮が足りないケースを含めたヒューマンエラーなど人的要因を介するもの。熟練したエンジニア不足が予想される近未来では、この問題は切実と言わざる得ません。
そして近年増えているのが、身代金目的のランサムウェア・マルウェアなどのサイバー攻撃や大手ITベンダーによる予想外の不具合発生です。こうしたものはいつ発生してもおかしくなく、また備えておくのが難しいのが実情なのです。
対策に必要な要素
突然のシステム障害に完全に備えることは難しいにしても、なにかしらの対策を講じたうえで効果的なリスク軽減策を準備しておくことは必要です。
緊急事態に黙って指を咥えて何もせず耐えしのぐのか?
素早く自動的にバックアップインフラ等に移行して切り替えられるかで危機対応能力に差がついてくると言わざる得ません。
そのため、たとえばフェイルオーバーシステム構築や障害発生につながりやすい事象を検出できるアラート、システムの稼働状況を常時モニタリング追跡できる体制整備などは課題解決になりやすいものと言えます。
さらに緊急時に備えた対応計画を策定、事前に十分なテストやシミュレーションをしておくこと。もはやシステム障害は企業にとどまらず、社会全体にインパクトを与えることが判明しています。そのため障害発生に備え利用可能なバックアップインフラを整備運用できることが求められ始めているのです。
認識
障害発生に備え即座に参照できるオフラインリソースやバックアップデータ等へのアクセスの確保、また緊急対応マニュアル整備や人員配置に関しても取り決めておくことが被害を少しでも少なくさせる可能性を高めます。
クラウドサービス等のシステム依存が強まるなか、緊急時への備えは喫緊の課題となっており、問題が発生することを前提とした動きや備えをすべきタイミングです。こうした問題は今後も企業経営を左右しかねない重要な要素をはらんでいるのです。